
変わり続ける時代の中で、新たな医療を創り出そうと挑み続ける医師たち。そのチャレンジの根底にあるもの、その道程に迫ります。
創人
被災地や事件現場に駆けつけ
救命に全力を尽くす救急医
hippocrates 24号 2025年02月発行
脳神経外科で経験を積みながら救急医療の道へ
-
解剖学の研究者だった父に連れられて、幼少期から研究室に出入りしていたという布施明先生。ホルマリンの匂いのする標本室に入るとそこは異世界の雰囲気だったが、不思議と気持ちが落ち着いたのを覚えている。父の影響で医療は常に身近にあり、物心がついた頃から「医師になって患者さんの治療がしたい」と思うようになっていた。
宮崎医科大学(現・宮崎大学医学部)に入学した布施先生が興味を持ったのは、脳神経科学だ。
「ハンマーのような打腱器を使って身体の反応を見ながら、この反応があれば病巣の部位はこのレベルだと、画像診断と比較してロジックに判断できるのがとても面白かったんです」
-

大学卒業後、脳神経外科で働くようになると、医師人生を変える出来事があった。病院内で事故があり、患者が救急室に運ばれてきた。そこに駆け付けたのが、まだ医師になったばかりの布施先生だった。他の医師が来る前に診断し、応急処置をする。後から振り返ると緊張性気胸の可能性があったが、それを見抜けなかった。最善は尽くしたが、結果的に患者さんを助けられなかったことで、布施先生の胸には「もっとできることがあったのではないか」と、消えない後悔が残った。
「この経験をきっかけに、脳神経外科だけでなく、救急医療を学ぼうと決意しました」
それならばと選んだのが、日本医科大学の救急医学教室だった。当時から「救急といえば日本医科大学」といわれるほど、高度な救急医療を実践していたからだ。1990年、布施先生が医師になって2年目のときに救急の道へ足を踏み入れた。
日本トップクラスを誇る救急医療の“最後の砦”
-

院内防災訓練にて

国民保護共同訓練にも参加
-
日本医科大学付属病院高度救命救急センターでの怒涛の日々が始まった。今でこそ医師の働き方改革が叫ばれているが、当時、家に帰れるのは月に3、4日。ハードだったが、充実感があった。
「遠方から搬送されてくる患者さんも多くて、初療室の廊下にまで患者さんが溢れていました。それでも受け入れを断らなかったのは、ここで患者さんを診なければ、他に対応できる病院がなかったからです。医師たちには、“ここが最後の砦だ”という意識が強くありました」
多くの患者さんに対応するうちに、救急医としての腕が磨かれていった。布施先生は、その上でさらに脳神経外科の専門性を身につけることにした。日本医科大学脳神経外科学教室に出向して、脳神経外科専門医を取得した。
さらに、新たな治療法として注目を集めていた脳血管内治療の技術を習得するためにフランスに留学。パリ大学附属ビセットル病院神経放射線診断治療部門のピエール・ラスジャニアス教授のもとで、世界最先端の治療法を学び、帰国後、救急医としては全国ではじめて脳血管内治療専門医も取得した。
そうした学びは、救急医療の現場でも大いに役立っているという。
「救急科では患者さんの初期診療にあたり、その後、脳神経外科や心臓血管外科などの診療科の先生方に治療をお願いすることがあります。自分でも専門分野を学んだからこそ、どこまで自分たちで診て、どこから専門の先生に依頼するのがよいのか、その見極めがスムーズにできていると感じます」
救急医療において、各診療科の医師たちとの連携は欠かせない。布施先生をはじめとする救急科の医師たちは、その連携の要として力を発揮している。
災害で発生する“未治療死”
データ解析でリスクを予測
救急指導医としての診療とともに、布施先生が力を入れているのが災害医療の研究だ。これまで数々の災害現場に赴き、医療支援を行ってきた。東日本大震災では発災急性期に宮城県気仙沼市に入り、厳しい被災地の状況を目の当たりにした。
「日本の災害医療は、阪神淡路大震災をきっかけに被災後の対応について振り返り、それをもとに教訓を積み上げてきた歴史があります。どんどんバージョンアップされていく一方で、私の中に『本当にそれだけで大丈夫なのだろうか』という疑問が生まれました」
例えば、阪神淡路大震災での教訓は、津波被害の大きかった東日本大震災では必ずしも応用できず、災害の規模や立地などによって取るべき対応は異なる。今後、甚大な被害が発生するといわれる首都直下地震や南海トラフ地震に備えるためには、どうすればよいのか。
そこで布施先生が取り組んだのが、「災害医療シミュレーション・システム」の開発である。発災後の“未治療死”に焦点を当ててデータを解析した。未治療死とは、発災後、災害による直接死を免れたものの、適切な治療を受けられずに亡くなること。これまでも災害現場では未治療死が起こっていたが、すべて災害死としてまとめられてしまい、明確なデータが示されることはなかった。
研究グループが愛知県などの8府県について試算したところ、およそ12万人の重症者が出て、うち9万人が未治療死となるという推定データが導き出された。
「未治療死を防ぐためには、限られた医療資源を適切に配備することはもちろん、防災、減災対策が重要です。私たちのシミュレーションでは、防災対策によって未治療死を大幅に減らせることも明らかになりました」
それと同時に、布施先生が声を上げるのが医療人のスキルアップだ。
「すべての医療人が災害医療を専門的なレベルで行えるように、教育していく必要があります。災害医療はできて当たり前というレベルまで根付かせなければ、これだけ災害の多い日本で、安定した医療を提供していくことはできません」
【日本医科大学付属病院の高度救命救急センター】
日本医科大学付属病院の高度救命救急センターは、国内で初めて開設された救命救急センターとして50年の伝統がある。年間約2万人の救急患者と8500台の救急搬送に対応しているが、そのうち他院からの紹介も含めて重症救急患者は約1700人。救急の“最後の砦”としての役割を果たしているのである。現在、院内の各診療科の医師たちと連携しながら、救命救急科専属の医師40名と看護師140人体制で、チーム一丸となった質の高い医療を提供している。
-

新たに導入されたドクターカー
-

カンファレンス風景
事件現場で応急処置をする
警視庁IMATの立ち上げ
2012年には、布施先生の尽力によって警視庁にIMAT(事件現場医療派遣チーム)が立ち上がった。IMATとは、バスや船舶などの乗っ取りや立てこもりなどの重大事件の際に、あらかじめ後方に待機し傷病者の応急処置に当たる部隊である。
-
「当院の救急医が現場にいることで、何かあったときにすぐに対処できる。わが国ではじめて運用を開始したのは日本医科大学ですが、いずれは全国へと広げていきたい」
IMAT発足のきっかけになったのは、2007年に愛知県長久手で起きた立てこもり事件だった。対応した警察官が発砲されて殉職した。そして2008年の秋葉原無差別殺傷事件では出動した医療チームが危険に晒された。IMATの発足は、現場の警察官、医療チーム双方からの強い要望で誕生した。さらにIMATの活動は、海上保安庁の職員受傷時の救護活動の連携にも発展した。布施先生は「海上保安庁メディカルコントロール協議会」委員として活動をけん引している。
30年以上にわたって救急医療に邁進してきた布施先生。救急医のやりがいは何だろうか。
「医師として一つ一つの専門的な手技を極めるのはもちろん素晴らしいことですが、それと同時に救急搬送された患者さんの命を救うために目の前の一つ一つの命に真摯に向き合い続けることも、同じようにやりがいがあります。救急医にとって大切なのは、何とかして患者さんを助けたいという強い思い。私は尊敬する救急医の先輩たちから、そうした姿勢を学びました」
今、目の前にいる患者さんのために力を尽くす。それが布施先生の変わらぬ矜持なのである。
-
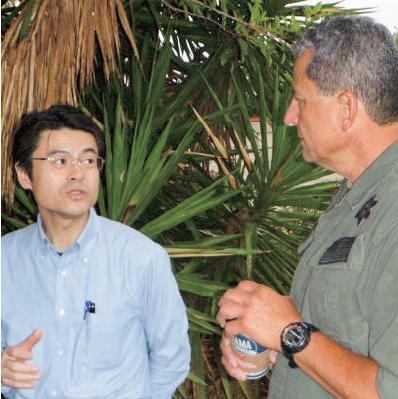
米国ロサンゼルスでSWAT(特殊部隊)を視察

警視庁IMAT協定式

布施 明先生(ふせ・あきら)
日本医科大学医学部救急医学 教授
日本医科大学付属病院 救命救急科/
高度救命救急センター 教授
1989年宮崎医科大学卒業。1996年に日本医科大学大学院医学研究科救急医学にて医学博士を取得。同大学付属病院高度救命救急センターでの勤務を経て、1998年に仏国パリ大学附属ビセットル病院神経放射線診断治療部門に留学し、脳血管内治療を学ぶ。厚生労働省医療技術参与、内閣官房国民保護訓練評価委員などを歴任。


